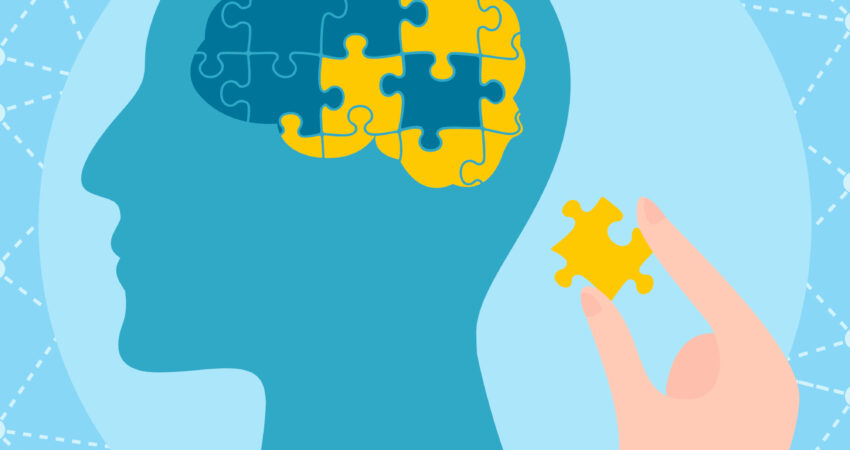
自社サイトを限られたリソースで運営しているとぶつかる壁が、内部施策と外部施策についてどちらを優先するかという問題です。しかし、そもそも内部対策と外部対策との違いや、それぞれにどのような効果が期待できるのか疑問に思っている方も多いでしょう。そこで本記事では、内部対策と外部対策の違いや優先順位、対策方法について解説します。
目次
自社サイトの内部を整備し、SEO評価を上げることを目指す施策を「内部対策」といいます。たとえば、Googleの場合、検索結果に表示する前にサイト内をロボットであるクローラーが巡回します。クローラーが巡回を行い、サイトやページを検索結果に表示する価値があると判断したときに、はじめてインデックス(検索結果に表示)されます。そのため、内部対策はクローラーが巡回しやすいような構造づくりや、コンテンツの充実などの施策を行うのが一般的です。内部対策にはおもに、次のような例が挙げられます。
自社サイト内で完結する内部対策とは対照的に、外部からの評価やつながりを増やしてSEO評価を高める施策を「外部対策」といいます。外部対策はおもに次の2つを獲得するための施策を行うのが一般的です。
SEO評価を上げるためには、外部からの自社サイトの評判や人気も重要な要素の一つといわれています。評判や人気を確認するための方法として、検索エンジンは被リンクの数やサイテーション(口コミなど)の評判を判断基準にしています。ただし、被リンクを増やす際に気をつけたいのが、リンクの売買や過剰な相互リンクです。こうした行為は、Googleのポリシー違反と判断される可能性があります。Google ウェブ検索のスパムに関するポリシーでは、次のような行為はポリシー違反になる可能性があると記載されています。
ポリシー違反にならない外部対策としては、おもに次のような施策が挙げられます。
内部対策と外部対策は効果をより高めるためにも、優先順位を決めて進めるのがおすすめです。では、内部対策と外部対策はどちらが重要なのか、外部対策はどのようなメリットがあるのかを解説します。
より優先順位が高いのは「内部対策」であるといわれています。というのも、いくら外部対策を頑張っても、内部対策に問題があると検索エンジンからの評価が上がりにくいためです。評価されるコンテンツが少なかったり、構造がわかりにくかったりする場合は、外部対策の効果が不十分になります。反対に、内部対策を行うことによって注目されるコンテンツが増え、自然な被リンクやサイテーションの獲得につながるケースも少なくありません。そもそも、いくら外部対策によって上位表示したとしても、サイトを訪れたユーザーに魅力を感じてもらわなければ、資料請求やお問い合わせなどのコンバージョンにつながりません。まずは内部対策を行ってから、外部対策を行うのが理想的です。
「外部対策は効果がなくなった」「意味がない」といわれることもありますが、実際にGoogleはページの評価を行う際にリンクを基準としていると言及しています。
Google では、200 以上の基準と、PageRank™ アルゴリズムをはじめとするさまざまな技術を使用して、各ウェブページの重要性を評価しています。特許を取得した PageRank のアルゴリズムでは、ページ間のリンクを「投票」と解釈し、どのサイトが他のページから最も良い情報源として投票されているかを分析します。
このように、Googleは被リンクやサイテーションをもとにサイト内のコンテンツの価値を判断しています。ただし、被リンクは数ではなく質が重要視されます。かつては有効といわれた「リンクスパム」の効果はなくなったものの、権威のあるサイトからの被リンクや良質な被リンクの数は、まだまだSEO対策としては有効といえるでしょう。
内部対策の施策はおもに3種類に分けられます。
マイナスな評価を受けないように検索エンジンのクローラー対策と、ユーザーに向けた施策をあわせて行うことで、SEO評価を向上できるといわれています。
検索エンジンのクローラーが巡回を行う際に時間がかかると、インデックスされなかったり、クロールの頻度が下がったりするというデメリットがあります。そのため、検索エンジンにコンテンツを読み取ってもらう対策を行います。
Google ウェブ検索のスパムに関するポリシーによると、キーワードの乱用はポリシー違反になる可能性があります。対策キーワードを入れるときは不自然な文章になったり、キーワードを羅列したりすることがないように気をつけてください。また、検索エンジンのクローラーは画像を認識できません。そのため、altタグを設定することで、どのような画像なのか読み取ってもらいやすくなります。
検索エンジンのクローラーが素早く巡回できるように促進する対策として、次のような施策が有効といわれています。
クローラーは外部リンクやXMLサイトマップを優先的にクローリングするといわれています。そのため、内部構造をわかりやすくしたり、外部リンクが不足している場合は、外部対策をあわせて行ったりするのも一つの方法です。また、「www」の有無をなくしてURLを統一するなど、状況にあったリダイレクトを行うのも内部対策の方法として挙げられます。
301リダイレクトと302リダイレクトの違いとは?設定方法と活用シーンを解説
ユーザビリティを高める対策として、次のような施策が有効といわれています。
ページの表示速度を上げるためには、画像を圧縮したり、フォントの変更を減らしたりするのも一つの方法です。また、Googleアナリティクスやリスティング広告など、複数のタグを設置している場合は、Googleタグマネージャーをはじめとするタグマネジメントツールを使ってタグを一元管理すると、ページの表示速度が上がるといわれています。隠しテキストや隠しリンクは一見すると見えないため、設置する方もいるかもしれませんが、ガイドライン違反になるためやらないことをおすすめします。
Googleタグマネージャーとは?覚えておきたい基本用語と設定方法
外部対策は次のような施策が有効といわれています。
外部対策の基本は「自然かつ質の高い被リンクやサイテーションを増やすこと」です。被リンクの購入やサテライトサイトからの被リンクはポリシー違反として、ペナルティの対象になる可能性があるため注意が必要です。
被リンクやサイテーションを自然に増やすのに適しているのがSNSです。SNSにはさまざまな種類があるので、一つのコンテンツから複数のクリエイティブを作成できるほか、拡散効果も期待できるため、同時にいくつものSNSを運営している企業がほとんどです。自社サイトや自社の認知度拡大にもつながるので、有効活用してみてください。
nofollow(ノーフォロー)属性の役割とは?SEOにおける効果と使い方
どんなに被リンクを集めたサイトでも、中身のコンテンツやユーザビリティで評価されなければ意味がないため、外部対策よりもまず内部対策が優先といわれています。しかし、クリーンなサイト運営を心がけるだけで内部対策につながっているケースもあるため、対策として取り組む必要があるのは外部対策といえます。内部対策や外部対策はやるべきことが多く、実際に行っても果たして効果が出ているのか検証しにくいという方もいるでしょう。そのようなときはSEOの専門家に相談するのがおすすめです。限られたリソースをうまく使い、効率的なサイト運営を目指していきましょう。
SEO最新情報やセミナー開催のお知らせなど、お役立ち情報を無料でお届けします。
